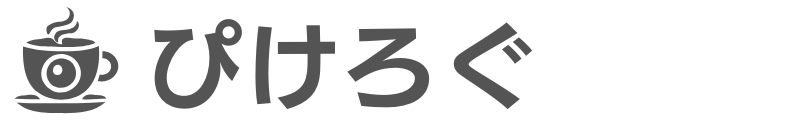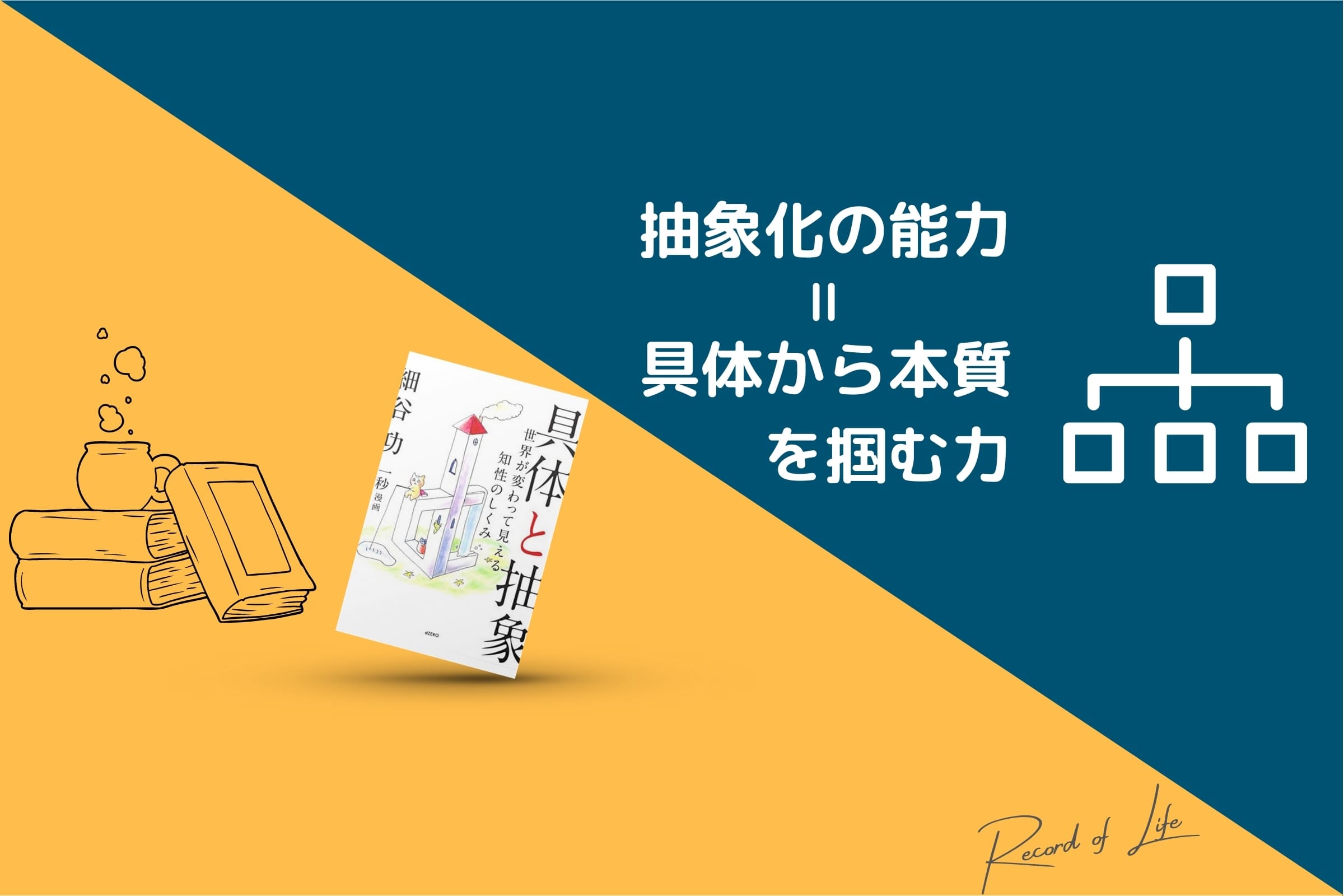【目次ピック】「具体と抽象」の目次から3つを深掘り
こんにちはぴけです。
今回の本は、細谷功さんの「具体と抽象」です。
この本では、人が無意識のうちに行っている具体化と抽象化を分かりやすく論理的に説明しています。
なかなか議論がかみ合わない人やたくさんの情報から本質を見抜く能力を身につけたい人におすすめです。
本記事では、本の中から3つの目次をピックアップし、自分の経験や解釈をいれながら解説していきます。
ピックアップ目次
- 法則とパターン認識 一を聞いて十を知る
- 本質 議論がかみ合わないのはなぜか
- 階層 かいつまんで話せるのはなぜか
法則とパターン認識 一を聞いて十を知る

抽象化とは複数の事象の間に法則を見つける「パターン認識」の能力ともいえます。身の回りのものにパターンを見つけ、それに名前をつけ、法則として複数場面に活用する。これが抽象化による人間の知能の凄さといってよいでしょう。 ー引用ー
この章では、人が暗黙のうちに抽象化の能力を多用していることを再認識しました。
コミュニケーションを例にして考えると、初対面の人とでもある程度会話ができるのは、過去のコミュニケーションの経験から、抽象化してパターン認識することで、具体化した初対面の人との会話に転用しているからです。
抽象化がないと、それぞれの人ごとに会話をするのがひと苦労であることが容易に想像できます。
つまり、人は無意識のうちに点と点を線でつなげるということをたくさん行っているということです。
本質 議論がかみ合わないのはなぜか

「具体と抽象」というのは、「目に見えるもの(こと)と身に見えないもの(こと)」「表層的事象と本質」といった言葉にも置き換えられます。このような視点で、つまり「抽象度のレベル」が合っていない状態で議論している(ことに両者が気づいていない)ために、噛み合わない議論が後を絶たないのです。 ー引用ー
このことから、意見が噛み合わないとき、はたして自分は、相手と同じ抽象度のレベルでの議論をしているのかという意識が持つことができます。
このことを意識するだけでも相手との意見の食い違いは、少なくなります。また、同じ抽象度での議論である場合は、両者にとって有益な議論をすることができます。
記事を書いている僕自身、相手と抽象度を合わせた議論はまだまだできていないので、相手がどの抽象度の話をしているかを常に意識しています。
階層 かいつまんで話せるのはなぜか

抽象化して話せる人は、「要するに何なのか?」をまとめて話すことができます。膨大な情報に目にしても、つねにそれらの個別事象の間から「構造」を抽出し、なんらかの「メッセージ」を読み取ろうとすることを考えるからです。 ー引用ー
抽象的な事象から具体化した事象に落とし込むことは、簡単です。
反対に具体的な事象から抽象化した事象に落とし込むのは、難易度が上がります。
つまり、具体的な事象から抽象化した事象に落とし込む力が抽象化の能力であることがいえます。
したがって、かいつまんで話せる人は、抽象的なレベルで理解し、具体化しているということです。
僕自身、この本のブログを書くことで、本の内容を抽象化し、自分自身の言葉で具体化することで具体と抽象の練習をしています。
まとめ
今回は、「具体と抽象」という本についてでした。本の内容自体が、具体と抽象を繰り返して説明しているので、読みながら、感覚的にも具体と抽象を理解できます。人が無意識のうちに行っている能力だからこそ意識することで能力をより向上させることができます。
この記事を読んで気になる方は、ぜひ書籍を手にとってみてください。
おすすめ書籍

【目次ピック】「いつも機嫌がいい人の小さな習慣」の目次から3つを深堀り
ピックアップ目次
・意識して「ゆっくり丁寧に」動く
・だれも見ていないところで、いいことをする
・悩みは「どうして?」ではなく、「どうしたら?」で考える

【目次ピック】「昨日も22時に寝たので僕の人生は無敵です~明日が変わる大人の早起き術~」の目次から3つを深堀り
ピックアップ目次
・早起きは一生使える武器
・ベッドに入る時間を固定する
・朝の支度をてきぱきとこなす